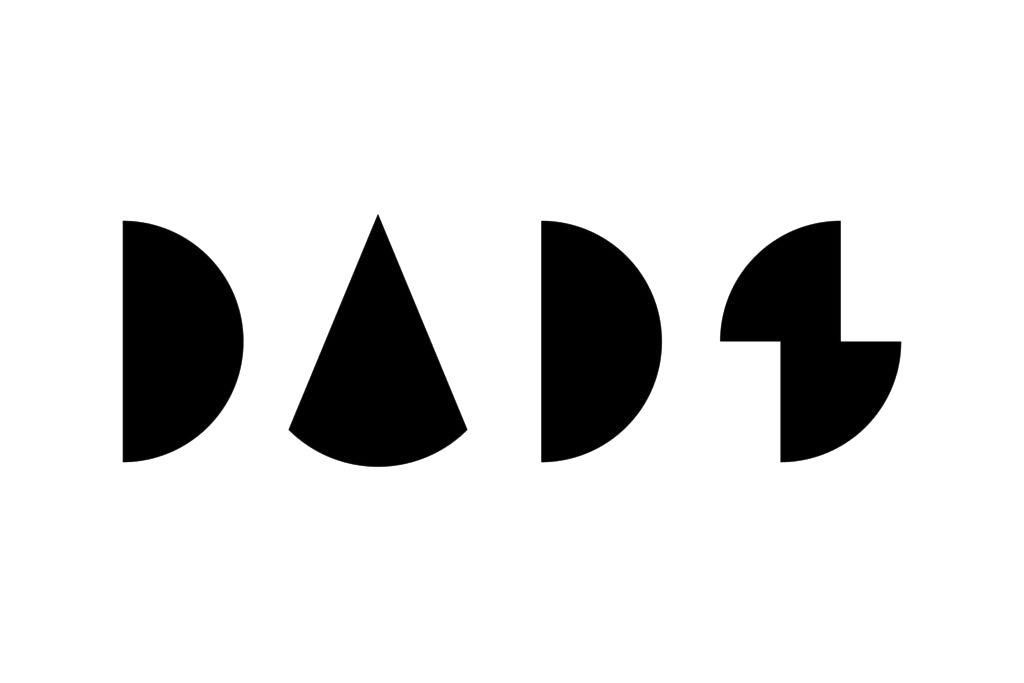内池陽奈によるコラム「よしなしごと」を不定期にお届けします。
*
夢を見ていた。
幼稚園の学芸会でやった劇の記憶。なんの話をやったのかは覚えていない。私の役割は〈ナレーター〉だった。今思えば、園児の数に比べておはなしに登場するキャラクターの数が足りなくて、無理矢理に作り出された役割だった。クラスの半数は〈ナレーター〉だったと思う。当時はなんとも思わなかったが、随分とお粗末な比率だ。
ともかく、当時の私は〈ナレーター〉をやった。特別な衣装が用意されるわけでもなく、いつもの制服にテロンテロンな生地のバカでかい蝶ネクタイをつけて、私はたった一行のセリフを言うだけでやきもきしていた。耳の先までわかるくらい顔がこれでもかと熱くなり、本番直前にどうしてもトイレに行きたくなって、しかし緊張からトイレに駆け込む足も震えてしまい動くことができず、色んな意味で人生の危機を覚えていたのを思い出した。
いちばん安易な役をこなすことで精一杯だった小さな私。思えばこれが、私の原点であり、本質なのだと思う。
そんな追憶を、夢の中でしていた。
◆◆◆
私は、自分のことを、小市民だな、と思う。
これは単にプチブルというニュアンスではなくて、米澤穂信先生の〈小市民シリーズ〉に出てくる意味合いでの小市民だ。言い換えれば、「平凡」。
かつての私は、自分を特別だと思っていた。
泳げるし、ピアノが弾けるし、計算は早いし、字は上手い。絵を描いたらクラスで一番。私はクラスで一番才能に溢れている。小学生の私はそう思っていた。
でも実際偉かったのはそれら全てを習い事で習得させた親であり、払った金額だけの能力を手に入れていたに過ぎず、運良くクラスにそれ以上の境遇の人が居なかっただけだったのだ。
それに気づいたのは一学年50人程の小さな小学校を卒業して、一学年に300人弱の生徒がいる中学校に入学してから。各分野で上には上が居たし、全てにおいて私以上の人なんてザラにいた。
その時私は、全てを悟ったのだった。私は、小市民だ、と。
それからの私は最悪だった。「頑張る」ということを放棄したのだ。もともと私は自分に甘いタイプで、私のありとあらゆる能力の値は直ぐに平均以下に成り下がった。怠惰な気持ちだけが残り、図体と虚栄心ばかりがすくすくと育った。才能も無ければ努力もしない。度胸も無ければ覚悟も無い。そんな人間になっていった。
そんな人間でも、(自称)進学校に身を置いた以上、大学進学率ほぼ100%の環境下で、流されるままに大学受験というものをした。明確なモチベーションもないままろくに勉強もせず、親に学習塾の月謝を払わせ続けていた。そのありがたい学習塾にも行きたくなくて、夏期講習をサボって山手線一周の旅をしたこともある。そんなだから、もちろん受験は惨敗。
最終的に身を置くことになったのは、「名前がウケる」と見つけてろくに調べもせずに願書を出した大学。そう、我らがデジタルハリウッド大学である。
デジハリに入学しても私のスタンスはあまり変わらなかった。
新しいことを習得するぞと3DCGを始めてみたものの、最初からガンガン制作が出来る同級生に圧倒され、また私は不貞腐れた。思えば、私の中では0か100かしか無いのだろう。その道で一番に成れないのならば、その道は一切極めない。
そうやって不貞腐れて3DCGを諦めかけていた時、なんとはなしに受講した広告の講義で、私は衝撃を受ける。広告まみれのこの国に生まれて、私はその時まで「広告代理店」という業界があることを、恥ずかしながら知らなかったのだ。広告というものは、企業にそれぞれ広告部的なものがあって、そこが広告を作っている…?くらいにしか考えていなかったのだ。全く意識をしていなかった。世の中の全般に興味を持っておらず、社会の仕組みを全く理解できていない小娘だったのだ(おそらくそれは、今もである)。
兎にも角にも、広告を知って、私の十数年間眠っていた探究心というものが蘇った。柄にもなく努力をして、広告代理店のインターンに複数参加した。周りが凄くても、いつものように不貞腐れずに自然とやる気が湧き上がった。悔しくて、本気で泣いたこともある。
そして「広告」を勉強する中で、お金で買わずとも元来自分の中にあった才能に気づいた。
私には少なからず、言葉を操る才能がある(※個人の所感です)。
怠惰の暗闇を突如灯したこの小さな小さな才能を、私はどこで発揮したら良いのかわからない。でも私はこの武器を手にして初めて、頑張りたい、と思えた。世の中にはいろんな言葉の職業がある。コピーライター、スピーチライター、ゴーストライター、作家、…。正直そこに達するには、私には足りないものばかりある。着眼点、発想力、表現力、語彙、経験。私はまた、0地点に立ったのだ。
それでも不思議と、力はみなぎってくる。1でも3でも、牛の歩みの進化が今は楽しい。
何者でもない自分に焦りを覚えて、何者かになりたくて、もがきたい、と思うのだ。
◆◆◆
10年後も私は、「私は小市民です」と微笑んでいたい。
しかしそれが、誇張から謙遜に変わっていますように。